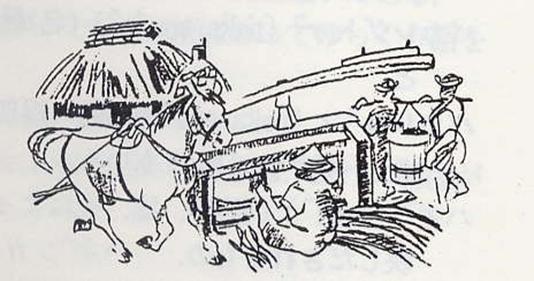公開日 2015年02月16日
耳取い (三下調子) (伝承地:東江上〉
〔系統:会所踊い系<しま歌。 踊の構成等:2人。二才踊い衣装。小道具:無手で踊る〕
一 暇伝馬の初積荷に 何積みせが右衛門尉
東仮屋の荷ががまや ゆらてが右衛門尉
ハーリヌヨーヤッサー
踊り手囃子 スリスリ ナヌシヌ ウムティカヨリバ
シタンナガハシ スリスリ
二 二、三線揃らち 掻ち鳴らす音や
音聞きば昔 思いたちゅさ
ハーリヌヨー ヤッサー
踊り手囃子 スリスリ ナヌシヌ シラハマナギドウシ
シューマシュ シラシヤワ スリスリ

大意
一 正月休みで空になった伝馬船の初荷に何を積もうとしているのか、右衛門尉。
東の仮屋(役所)の荷物が多いようだけど、ゆらてが(未詳)右衛門尉。
二 二、三線を取りそろえ、威勢よく弾き鳴らし、その音色に耳を傾ければ、昔の若
い頃が思い出されるよ。
語意
いとまてんま=からの伝馬船。 はっつんに=初積み荷。 うやむんじゃ=人名。右衛門尉。 あがりがいや=東の役所。 にががまや=荷が多い? ゆらてが(うわてが)=未詳。 にさんしんすらち=二、三線を揃えて。 かちならす音=勢い良くつま弾く音。 思いたちゆさ=思い出すよ。
解説
民謡工工四と大同小異。語釈「いとまてんま」は、やまとてんまの誤りかと中原メモにある。これも鹿児島の民謡研究家に照会したが原歌も類歌も見当たらないとのこと。「はっついんに」は初荷のことだろう。「うやむんじゃ」を中原メモでは人名「右衛門尉」ではないかとある。しかし薩摩語の「多かもんじゃ」の訛りではないかとのヒントを得た。「いとまてんま」は港につないである伝馬船のこと。暇伝馬である。「あがりがいや」は上の役所、または東りの役所と解せらる。仮屋(かいや)は一般に役所をいう。「にががまや」は荷が多かということか。 〔『伊江村史』 上巻569頁〕
見直し
荷取い→耳取い 右衛門者 → 右衛門尉。 寄らてが → ゆらてが。 御三線 → 二、三線。
※「荷取い」から「耳取い」へと元に戻すにあたっては、本委員会としては確証がもてない。従って、なお、将来への研究課題としてもらいたい。
主な解釈
- 題名の「耳取り」は踊りだしの動作が耳を取るようにして踊るので、その名がつけられたのだろうと解される『伊江島の村踊り』27P
- 正月で休んでいた伝馬船が初荷を積み始めた。何を積んでいるか、右衛門尉(役員)、東役所(仮屋)の荷が多いか、もうすんだか、と初荷の威勢のよさを作詞した歌である。(南風原町第6回民俗芸能交流大会に提出した解説79P)
荷取い(耳取い)の呼称あれこれ
- 耳取 1956 昭和31年9月16日 農協50トン工場落成式
- みみとい 1958 昭和33年6月18日 第6回全琉協同組合大会余興出演
- みみとい 1959 昭和34年10月 川平朝申氏現地調査
- 耳取 1967 昭和42年 『伊江村誌』
- みゝとい 1969 昭和44年12月30日 『伊江島民謡工工四』
- 耳取 1971 昭和46年9月 26日 米寿祝い(東江上上演)
- 耳取り 1978 昭和53年3月 『伊江島の村踊り』
- 耳とい 1980 昭和55年3月 1日 『伊江村史 上巻』
- 耳取 1982 昭和57年11月 3日 伊江村民俗芸能発表会(1巡目)
- 荷取い 1984 昭和59年11月11日 南風原町第6回民俗芸能交流会
- 荷取い 1985 昭和60年 9月 3日 『民謡と舞踊曲工工四』
- 荷取い 1990 平成 2年11月17日 伊江村民俗芸能発表会(2巡目)
- 荷取い 1993 平成 5年 8月28日 伊江島の村踊り公演
- 荷取い 1997 平成 9年 3月31日 『伊江島民謡舞踊曲工工四』
- 荷取い 1998 平成10年11月 8日 伊江村民俗芸能発表会(3巡目)
- 荷取い 2001 平成13年11月24日 文化庁企画第51回全国民俗芸能大会
- 耳取い 2006 平成17年11月12日 伊江村民俗芸能発表会(4巡目)